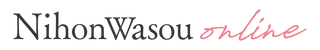—— 知れば知るほど奥深い、“きものの原点”のおはなし
着物はどの素材でも同じように見える——そう感じる方も多いのではないでしょうか。
たしかに、今はポリエステルなどの化学繊維でできた着物もたくさん流通しています。お手入れが簡単で、価格も手頃。初心者の方にとってはとても頼もしい味方です。
でも、少しずつ着物に慣れていくうちに、誰もが一度は耳にする言葉——「正絹(しょうけん)」。この“正絹”とは、日本の伝統的な着物に使われてきた素材——“絹100%”のことを指します。
絹は、自然が生み出した特別な繊維

絹(シルク)は、蚕(かいこ)が自分の体を守るために作る繭からとれる天然の動物性繊維です。
一本の繭からは、なんと1,000〜1,500メートルにもなる細い糸が取れます。
その糸をより合わせ、染め、織ることで、私たちが身にまとう“絹の布”ができあがります。
この糸は、見た目以上に優れた素材。
たとえば——
・肌触りがなめらかで、吸湿性・放湿性に優れる
・夏は涼しく、冬はあたたかい
・静電気が起きにくく、ほこりを寄せつけにくい
・光を柔らかく反射し、上品な艶を放つ
自然素材のなかでも、絹ほど人間の肌に近い成分(タンパク質)でできている繊維は珍しく、「第二の肌」と呼ばれることもあります。
絹は“高級素材”というだけでなく、快適さと美しさを兼ね備えた、理にかなった天然繊維といえるかもしれません。
日本は“絹の国”だった
じつは日本は、かつて世界有数の絹の生産国でした。
明治から昭和初期にかけて、日本の生糸(きいと)は輸出の花形産業であり、「日本の富の源」とまで言われたほどです。
特に群馬・長野・山形・福島などには、今も絹産業の名残を伝える地域が多く、世界遺産にも登録された「富岡製糸場」はその象徴。

“絹を通じて世界とつながっていた日本”というのは、あまり知られていませんが、知ると少し誇らしい気持ちになる歴史です。
日本人が絹を愛し、技術を磨き、織物文化を発展させてきた背景には、単なる経済的な理由だけではなく、“自然の恵みを美に変える知恵”があったのだと思います。
なぜ皇室は、いまも蚕を飼っているの?
日本で絹がどれほど大切にされてきたかを象徴するのが、「皇室養蚕(こうしつようさん)」の伝統です。
明治以降、歴代の皇后さまが自ら蚕を育て、絹糸を取る「養蚕の儀」を続けてこられました。
現在の上皇后美智子さま、そして皇后雅子さまも、この伝統を大切に守られています。
なぜ、皇室がいまも蚕を飼っているのか。
それは、単なる儀式ではなく、日本の“ものづくりの心”を象徴する行いだからではないでしょうか。
絹は、自然と人の手が調和して初めて生まれる素材です。
桑の葉を食べて成長する蚕を慈しみ、一つひとつの繭から糸を紡ぐ。
そこには、命をいただきながら美を生み出すという日本的な精神が息づいています。
皇室の養蚕は、その“自然と共に生きる知恵”と“伝統を未来へつなぐ責任”の象徴のようです。
“本物”が放つ艶としなやかさ
では、絹の着物は、化繊(ポリエステル)と何が違うのでしょうか。
一言でいえば「光の表情」と「動きの美しさ」に違いが感じられます。
絹は一本一本の繊維が三角形の断面をしており、光を乱反射して独特の艶を生み出します。
この“奥行きのある光沢”が、正絹の着物が放つ上品さの秘密です。
また、糸自体がしなやかなので、着る人の動きに自然に沿い、姿勢や立ち居振る舞いまで美しく見せてくれます。
一方、ポリエステルなどの化学繊維は、表面が均一でハリがあり、ツヤは強くても平面的。
光の加減で「テカり」に見えることもあります。
そのため、同じ柄でも、絹で織られた生地と化繊ではまったく印象が異なって見えるのです。
未来に残したい、“絹という文化”
しかし今、この日本の絹産業は大きな転換期を迎えています。
かつて日本各地にあった養蚕農家は、後継者不足や採算の難しさから激減。
現在、国内で流通する絹糸の多くは海外産に頼らざるを得ない状況です。
それでもなお、国内で養蚕を続ける方々は、誇りを持って糸を紡いでいます。
なぜなら、絹は「ただの素材」ではなく、日本人の感性とともに育まれてきた“文化”そのものだからです。
光の加減で移ろう艶、手にしたときの柔らかさ、着たときに生まれる佇まい——
それは、数値では表せない「心の豊かさ」を感じさせてくれるものです。
一枚の帯揚げや半衿でも、“本物の絹”を手に取ることが、絹文化を感じるきっかけになるでしょう。
絹を選ぶということは、伝統を未来へとつなぐ一歩でもあります。着物を通して文化に触れ、その価値を次の世代へ伝えていく。
そんな積み重ねこそが、私たち一人ひとりにできる「伝統の継承」のかたちかもしれません。
後編では——
次回の後編では、「絹と化繊の違いをもっと具体的に」掘り下げていきます。
お手入れ方法や耐久性、価格差の理由、そして「どんな人にどちらがおすすめか」など、実際に選ぶときに役立つポイントを詳しく解説します。
「絹ってすごい!」と感じた方も、「でも扱いが難しそう…」と思った方も、ぜひ後編もお楽しみに。
(後編につづく)
【シルクワンピースはこちら】
執筆:日本和装オンライン運営