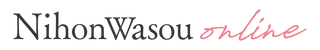■ 相撲ドラマを観ながら、ふと思ったこと
Netflixの『サンクチュアリ -聖域-』というドラマ、観た方はいますか?
相撲がテーマなのですが、ただのスポ根ものじゃないんです。
リアルで、熱くて、ちょっと過激で。私は観ながら、ずっと「伝統ってなんだろう」って考えていました。
土俵の上で繰り広げられる闘いだけじゃなく、力士たちの人間関係、葛藤、古い慣習と向き合う姿……そのすべてが、まっすぐで、痛々しくもあって。
「伝統って、守るだけでいいのかな」「問い直すことも、時には必要なのかも」——そんな気持ちになったのを覚えています。

■ 着物の世界にもある、“型”と“息苦しさ”
伝統といえば、着物の世界もそうかもしれません。
季節に合った柄や色、着る場面にふさわしい“格”、帯の結び方、そして細かい所作。
もちろん、そうしたルールや背景を知るのは素敵なことだし、そこにある美しさも大切にしたい。
でも同時に、「こうじゃないとダメ」と決めつけられると、なんだか窮屈にも感じてしまいます。
着付け教室でも、基本は丁寧にお伝えしています。でも、それがゴールじゃないんです。
本当の楽しさは、その先にある「あなたらしい着方」を見つけることだと思うから。
■ 「怒られそう」っていうイメージ、変えていきたい
「着物を着るのって、ちょっとこわい」
そんな声を聞くこと、あります。
たとえば、正絹の着物って聞くだけで、「高そう」「扱いが難しそう」「間違えたら恥ずかしい」……そんな気持ちになってしまう人もいるかもしれません。
『着物警察』という言葉があるくらいですから、実は私も昔はちょっとそう思っていました。
でも、それってそもそも「誰かに怒られそう」とか「間違えるのがこわい」と思わせてしまう空気が、着物業界のどこかにあったからかもしれません。
でも、今だからこそ、そこを変えていきたいんです。
“こうあるべき”じゃなくて、“こうしたい”を大切にできる着物の世界へ。
それもまた、ひとつの伝統のかたちだと思うんです。
■ 革新は、静かに、でも確かに

日本和装では、正絹の着物をもっと身近に感じてもらいたいという想いで、染織の職人さんたちと一緒にものづくりを続けています。
でも、「伝統を守る」ことだけが目的じゃありません。
たとえば、もっと軽やかに着られるように仕立てを工夫したり、汗ばむ季節でも快適に過ごせる素材を選んだり。
色柄も、ちょっと大胆に。今の感性にフィットするデザインも、どんどん取り入れています。
「品質を磨くこと」や「着る人のリアルな声に応えること」
それが、今の時代の“革新”なんじゃないかと思うのです。
■ 「自分らしさ」を軸にした、着物との付き合い方

正絹の着物って、特別な日だけのものだと思われがちですが、そんなことはありません。
ちょっと工夫すれば、もっと自由に、もっと心地よく、日常にも溶け込んでくれます。
たとえば、色数を抑えたシンプルなコーディネートで“こなれ感”を出したり、帯揚げや帯留めで遊び心を加えてみたり。
正解なんて、ひとつじゃないんです。
“正しさ”って、誰かから教えられるものじゃなくて、自分の心地よさを探るための道しるべ。
私は、そう思っています。
■ 着物にも、「今」のサンクチュアリを

ふと、思うことがあります。
いつかNetflixで、「着物を楽しむ現代の女性」が主人公のドラマが生まれたら——そんな日が来たら素敵だなって。
そこに描かれるのは、格式ばった世界ではなく、日々の暮らしに着物を取り入れながら、伝統と自分らしさのバランスを見つけていく人たちの姿。
そんな未来が映し出されたら、きっともっと多くの人が「着物っていいな」と感じてくれる気がします。
そしてもし、それが話題になって人気に火がついたら?
もしかしたら、日本だけじゃなく、世界中を巻き込んだ“本物のブーム”が訪れるかもしれない——そう想像すると、なんだかワクワクしてしまいます。
今日も、どこかで織られ、染められている一枚の反物。
その一枚が、やがて未来の文化の種になると信じたい。
そんな想いを胸に、私たちはこれからも、着付けを通じて十人十色の「あなたらしさ」にそっと寄り添っていきたいと思っています。
日本和装の無料着付け教室への応募はこちらから↓
再受講も歓迎です
執筆:日本和装オンライン運営